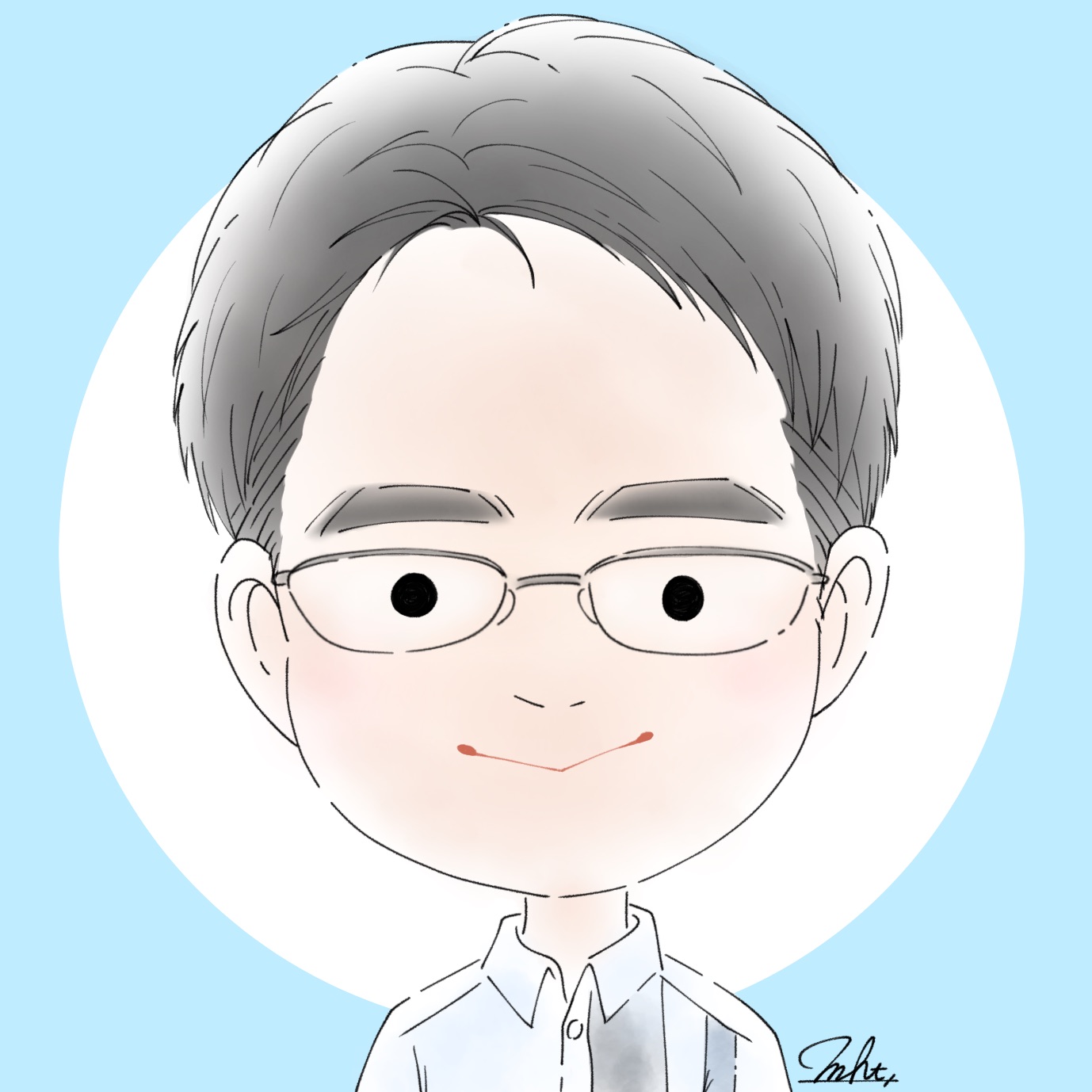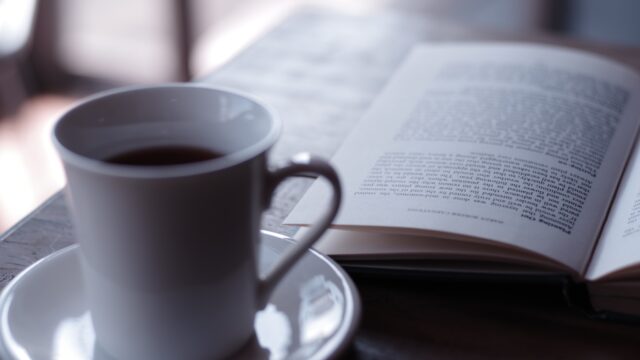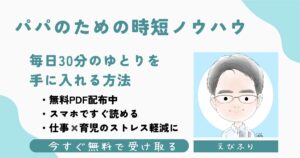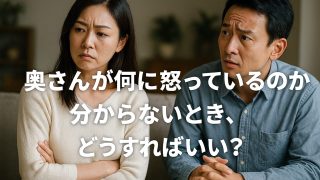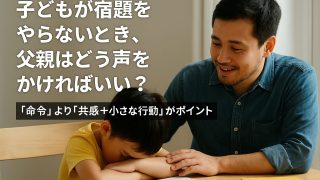えびふり(@ebifurya_alpha)です。
子育てする父親のよくある職場や上司との悩み

悩み1:上司が子育てを優先することを嫌がる
会社組織が子育てする父親を応援していたとしても、直接かかわる現場の人たちの理解を得られなければ子育てと仕事の両立は難しいです。とくに年齢層が高い上司や家庭よりも仕事優先で生きてきた人の中には古い考えをもっている人もいます。
父親が子どもの入学式や卒業式に有給休暇を取得して出席することは珍しくなくなりました。子どもの急病で病院の送迎をするための早退や遅刻も当たり前のようにできる時代です。しかし「ダメ」とは言わないけれど気持ちよく「いいよ」とは言ってくれない上司もいます。仕事が休みの日に家族サービスをするのは自由だけれど、仕事よりも子育てを優先することは理解できないのでしょう。とくに子育ては、父親だけでなく母親もいます。「なぜ、わざわざ父親まで必要なのか」と思うのかもしれません。
子育てはしたいけれど、上司の機嫌も損ねたくないという両方の思いに父親は悩みます。
悩み2:同僚や上司に迷惑をかけてしまう
子育てに協力的な上司や同僚にはありがたい気持ちでいっぱいになります。しかし一方で「負担をかけていないだろうか」と心配になります。子どもの急病で突然仕事を休むときには「迷惑をかけてしまった」と申し訳なく思います。とくに単身者が多い職場ではお互いさまというわけではなく、一方的に迷惑をかけている気持ちになることがあります。
子どもはあっという間に大きくなります。「今しかできない子育てをしっかりやりたい」という思いと「迷惑をかけて申し訳ない」という思いのはざまで父親は悩みます。
悩み3:職場の支援や制度がわからない
会社には福利厚生の一環として子育て世帯に支援や制度があることがあります。例えば、ベビーシッターを利用するときに補助が出たり、子どもの急病時に看護休暇が取得できたりする会社もあります。知っていれば有効活用して子育てをよりラクにすることができるでしょう。しかし、会社や担当社員によっては「子育ては母親が主体的にやるもの」という認識があり、子育て中の父親には使える支援や制度の内容を伝えていないこともあるのです。
「使える支援や制度は積極的に使いたい」と思っていても「父親だから」という理由で情報が入ってこないことに父親は悩みます。
だれでもできる対処方法
子育てする父親の職場や上司との悩みは、上手に妥協点をみつけることがよい解決のポイントです。ここからは、だれでもできる対処方法をお話しします。
上司の理解が得られるところから両立する
自分の上司が子育てに理解がない上司や考え方が古い上司だったとしても、上司を変えることはできません。また、理解がない上司に対して怒ることもよくありません。職場の雰囲気を悪くしてしまったら、周囲の人たちも嫌な気持ちになります。
対処方法は、上司の理解が得られるところから子育てと両立をする方法です。例えば、入学式や卒業式であっても「事前に有給休暇をとってまで子育て優先することはよくない」と考える上司がいたとします。しかし一方で、子どもの急病の場合は「突然の欠勤でもやむを得ない」と理解してくれたとします。上司には上司なりの判断基準があり「母親だけで対応可能な場合は休まないでほしい」と思っているでしょう。「こちらの要望をすべて理解してほしい」と思うのではなく、上司の理解が得られるところから両立することを目指しましょう。まずはこちらが歩み寄っていくことで、上司も少しずつ働きながら子育てをする父親を受け入れていくのではないでしょうか。
「助けてもらうとき」と「助けるとき」のメリハリ
「同僚や上司に迷惑をかけてしまう」と悩んでいる場合は「今は助けてもらうとき」と割り切って考えてみましょう。子育てを経験した上司や同僚ならば、子育てはあっという間に終わることを知っています。そして、子育て中はお互いさまであることも知っています。助けてもらったときにはしっかりと感謝の気持ちを伝えましょう。
単身者が多い職場では「自分ばかりが迷惑をかけている」と思うかもしれません。しかし「今は助けてもらうとき」です。いずれ単身者が結婚し子どもができれば立場は変わります。今度は「助けるとき」がやってくるのです。助ける側になったら、恩返しのつもりで助ければいいのです。
助けが必要なときに「助けて」と言える人は、助けを必要としている人がいたときにしっかりと助けることができます。
不明点は育休の先輩に直接聞く
会社の支援や制度について一番よく知っている人は、実際に働きながら子育て経験をしている先輩です。福利厚生の担当は総務部ですが、総務部の社員がすべてを把握しているとは限りません。「自分事」として真剣に調べたことがある経験者にはかなわないでしょう。
社内の子育てや育休の先輩とつながりをもっておくことは、その後も助けられることがあります。学校のPTAでは「おやじの会」という父親の集まりがあります。会社でも「おやじの会」を発足させておくと、子育ての悩みや仕事との両立についてのアドバイスを聞ける機会になるのではないでしょうか。
職場や上司との関係で悩まないために100%ではなく80%を目指そう!
仕事と子育てのどちらも完璧を目指すことはできません。子どもに急病はつきもので、子どもは仕事が休めない日に限って熱を出すものです。100%を目指せば、仕事と子育てのどちらかに無理がいきます。子育てを100%やろうと思ったら、上司や同僚の負担は大きくなるでしょう。子どもと直接かかわることだけが子育てではありません。働いてお金を稼ぐことも子育てに必要なことです。仕事も子育ても両立するためには、どちらかを100%にするのではなく、どちらも80%を目指すことです。そしてときには助けを求めることも両立を賢く乗り越えるコツです。
悪用厳禁ノウハウを無料プレゼント!
今回沢山の悩みを抱えている皆様に私がこれまでに学んだこと、試行錯誤の末に見つけた解決策を共有していきたいと思います。
例えば、下記のようなノウハウを提供しています。
- 家庭での時間を最大限に活用する方法
- 仕事でのパフォーマンスを向上させるテクニック
- ストレス管理とメンタルヘルスの向上
- 家族との関係を深めるコミュニケーションの秘訣
このノウハウで提供するのは理論だけではなく、実際に私が体験し、効果があった具体的な戦略と方法です。
こんな人におすすめです。
✅仕事と家庭の両立に悩んでる人、もっと上手にやりたい人
✅会社から早く帰ってきて、家族との時間を有意義に過ごしたい人
✅家族間のコミュニケーションを向上させたい人
登録フォームボタンを押して、ニックネームとメールアドレスの登録をお願いします。
まずはメルマガに登録してみて下さい。
メルマガに登録していただいた方に仕事と家庭の両立に忙しいあなたのための時間活用術をまとめた教材(PDF形式)『兼業主夫のための時間術』を無料でプレゼントします。
一緒に父親力マイスターを目指しましょう!